 暦いろいろ
暦いろいろ 八朔-旧暦8月1日
八朔は、旧暦の8月1日を指す言葉で、八月朔日を略した言葉です。旧暦8月1日は8月後半から9月後半くらいとなるため早稲の穂が実る頃であり、初穂を贈るなどの風習がありました。室町幕府が公式行事として採用したこともあり、今でも五穀豊穣・豊年祈願を祈って「八朔祭」を行う地域があります。
 暦いろいろ
暦いろいろ 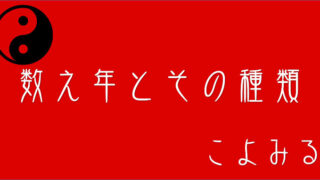 暦いろいろ
暦いろいろ  暦いろいろ
暦いろいろ  暦いろいろ
暦いろいろ  1月の歳時記・年中行事・記念日
1月の歳時記・年中行事・記念日  暦いろいろ
暦いろいろ  暦いろいろ
暦いろいろ 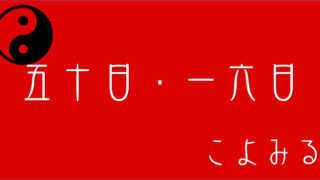 暦いろいろ
暦いろいろ