雉始雊(きじはじめてなく)は、七十二候の第六十九候の季節(略本暦による呼び名)です。
小寒の末候となり、「雄の雉が鳴き始める」という意味になります。
雉始雊について詳しく説明します。
雉始雊の読み方と詳しい意味
雉始雊の意味はどういう意味なのか、また読み方はどう読むのでしょうか?
雉始雊とは

雉始雊は、季節を72に分類した七十二候の1つで、概ね1月15日から1月19日頃の期間を表しています。「雉」は「キジ」と読みます。鳥のキジです。日本の国鳥にもなっています。
七十二候は、季節を24に分類した二十四節気を更にそれぞれ3つに分割しているので72個から成り立っています。
キジの産卵期は4月から6月くらいと言われていますが、西日本であれば2月くらいから産卵期をむかえることもあり、1月くらいから求愛行動としてオスのキジが「ケーン」と大きな鳴き声をあげるようになります。そのことから雉始雊は「キジが泣き始める季節」という意味となります。
オスは非常に綺麗な赤と緑色な鳥です。
なお日本の国鳥にもなっているキジは「ニホンキジ」と呼ばれる種類です。
雉始雊の読み方は?

雉始雊の読み方は「きじ はじめて なく」です。
雉は「きじ」です。「始」は「はじめて」とここでは読みますが「始めて」という漢字が使われているのは「始める」という意味で「初めて(最初に)」という意味では使われてないことが想像出来ます。
「雊」は「コウ」と読むのが一般的ですが、「雊」一文字で、雉が鳴くという意味もあります。
雉に見られる言葉・けんもほろろ

雉は「ケーン」となくと言われても多くの人は、その鳴き声を聞いたことがある人は今では非常に少ないと思います。
ただこの「ケーン」という雉の鳴き声は「けんもほろろ」の語源にもなっています。
「けんもほろろ」の意味は「愛想に人の頼みや相談事を拒絶して、取りつくしまもないさま。つっけんどんなさま。冷然としたさま。」ですが、この「けん」と「ほろろ」は共にっ雉の鳴き声が元だと言われています。
(「ほろろ」の「ほろ」は、雉の求愛行動の母衣打ちという説もあり)
「けんもほろろ」は室町時代には既に使われていたと言われる言葉で、求愛行動を行ったオスの雉が雌の雉に冷たくあしらわれる様子から生れた言葉とも言われています。
また「雉も鳴かずば撃たれまい」ということわざがあるように、よく鳴く鳥だったことが想像出来ます。
国鳥の雉は、昔はよく見られる鳥でしたが環境の変化等により急速に数を減らしており、滅多に見られない鳥となっています。
雉始雊-小寒の末候の時期
雉始雊の時期・期間は概ね1月15日から1月19日ころの5日間くらいです。
正確な期間は下記の通りです。
- 2021年:1月15日~1月19日
- 2022年:1月15日~1月19日
- 2023年:1月15日~1月19日
- 2024年:1月16日~1月19日
- 2025年:1月15日~1月19日
- 2026年:1月15日~1月19日
- 2027年:1月15日~1月19日
二十四節気は年によって期間が変わるため、七十二候もそれぞれ期間が年によって変化します。
同時期の中国(宣明暦)の七十二候の名称と意味
二十四節気・七十二候は元々中国で生まれたものです。二十四節気はほぼそのまま中国での書き方ですが、七十二候は中国のままだと意味が通じない部分や日本らしくない部分があり、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うように改訂され、「本朝七十二候」が作成されました。
現在では、1874年(明治7年)の「略本暦」に掲載された七十二候が主に使われています。
元々の中国(宣言暦)の七十二候は下記のようになっています。
- 名称:雉始雊 or 野雉始雊
- 意味:雄の雉が鳴き始める
「雉始雊」は日本でも中国でも同じものとなっています。
雉始雊に関すること
雉始雊に関することを紹介します。
雉始雊の季節感
雉始雊は100年以上前に考えられたもので、今の季節感にあっているかとと言えばキジ自体を見る機会が少なく、季節感があるのかどうかわからないというのが実際のところではないでしょうか?
ただ昭和初期までは日本の田園風景が広がる里では普通に見られた鳥でした。
意外と少ない動物園での飼育数
日本の国鳥にもなっているキジ(ニホンキジ)ですが、飼育している動物園は全国で20数か所しかないようで、あまり飼育されていません。
それほど飼育が難しい鳥ではないと言われていますが、あまり人気がないのかもしれません。
雉始雊に関するリンク
雉始雊に関するリンクです。

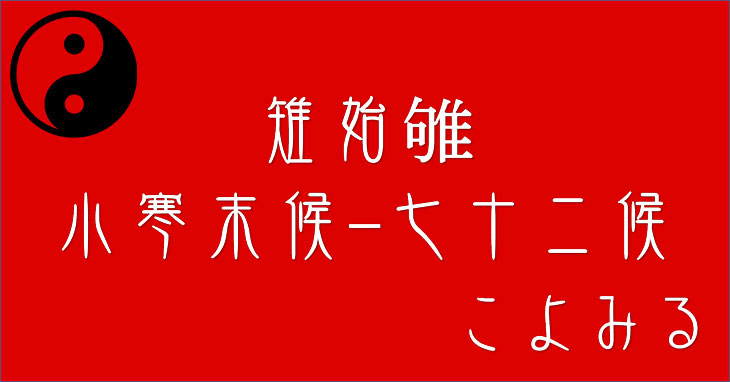
コメント